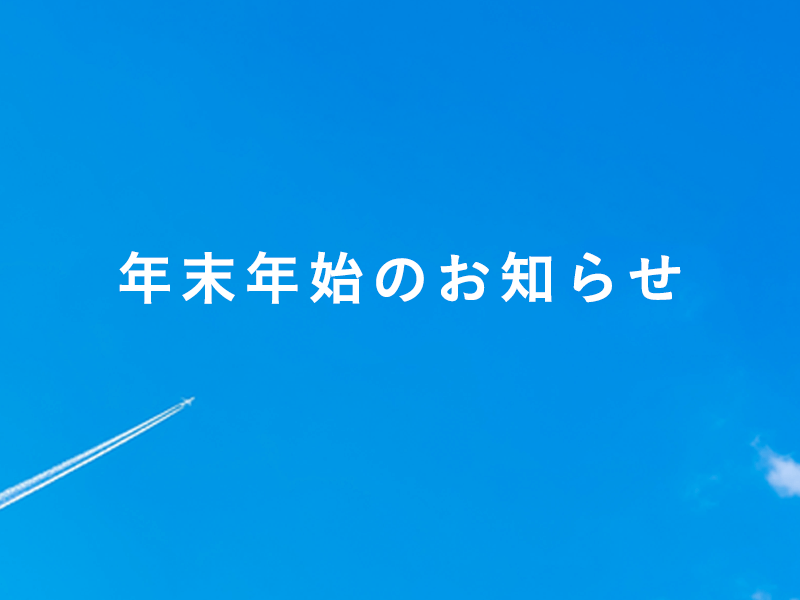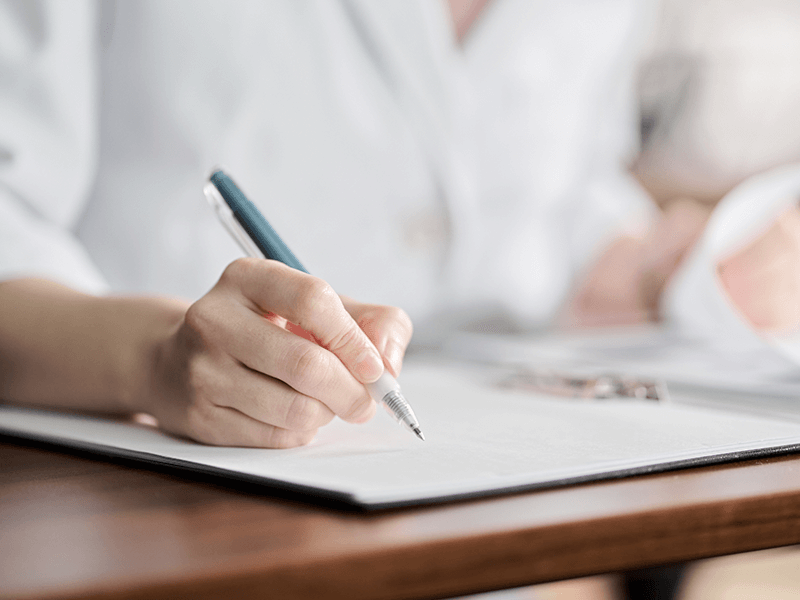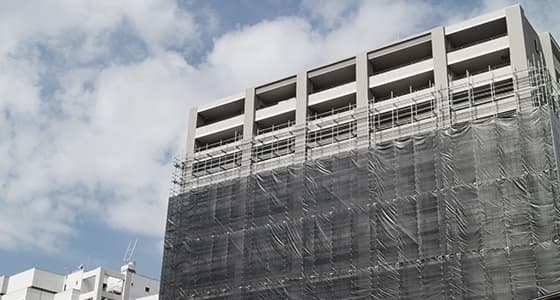TOPICS
-
年末年始のご予約・ご相談につきまして平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 年末年始のご予約、ご相談につきましてお知らせいたします。
-
日本弁護士連合会主催第14回事務職員能力認定試験 当事務所の合格者について2022年11月19日に実施された日本弁護士連合会主催第14回事務職員能力認定試験において、当事務所の所員8名が合格しま
-
訳あり物件買取プロ 監修記事掲載のお知らせ株式会社AlbaLinkが運営するWEBサイト「訳あり物件買取プロ」に、森田 雅也弁護士 が監修した記事が掲載されま